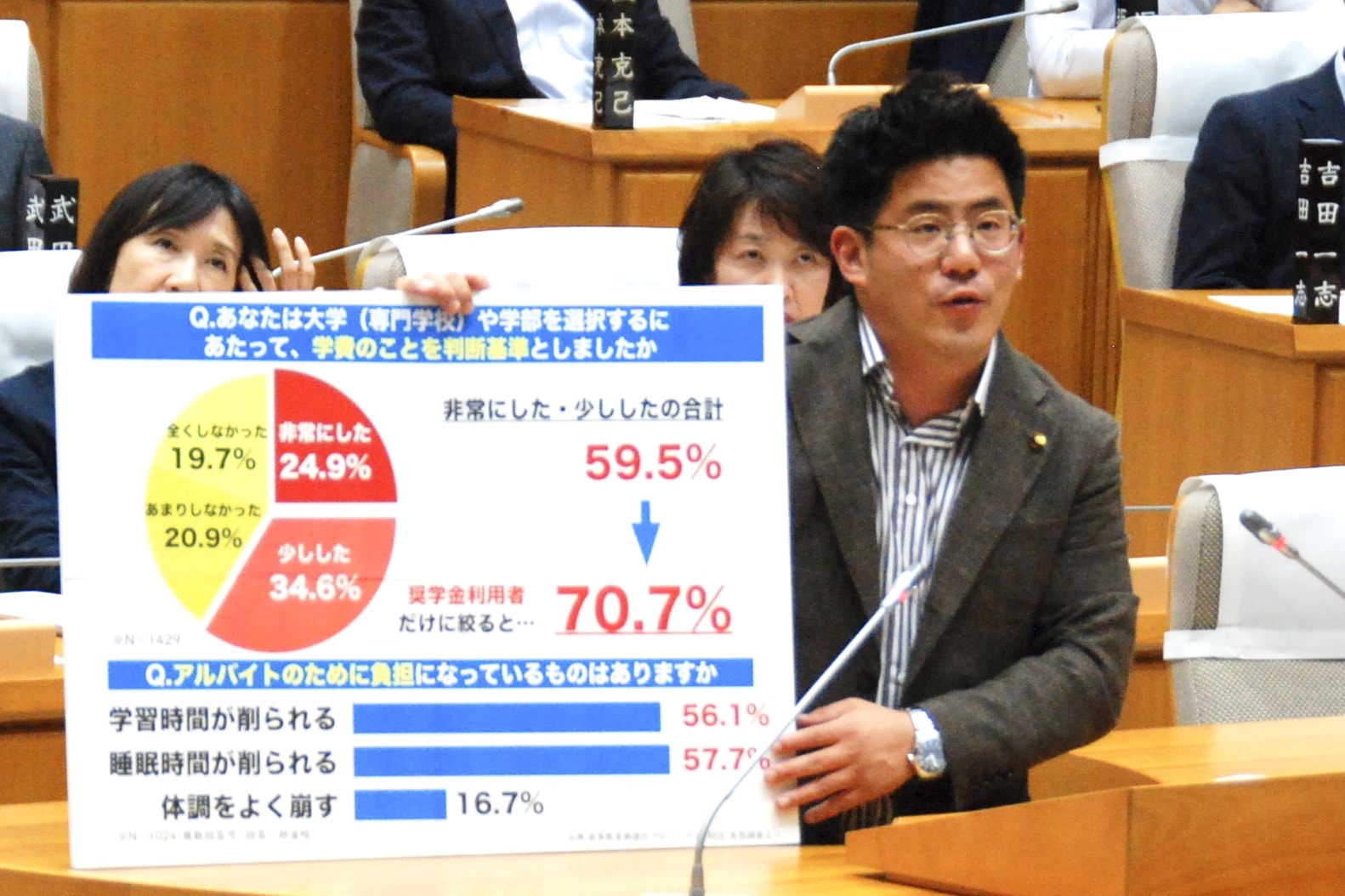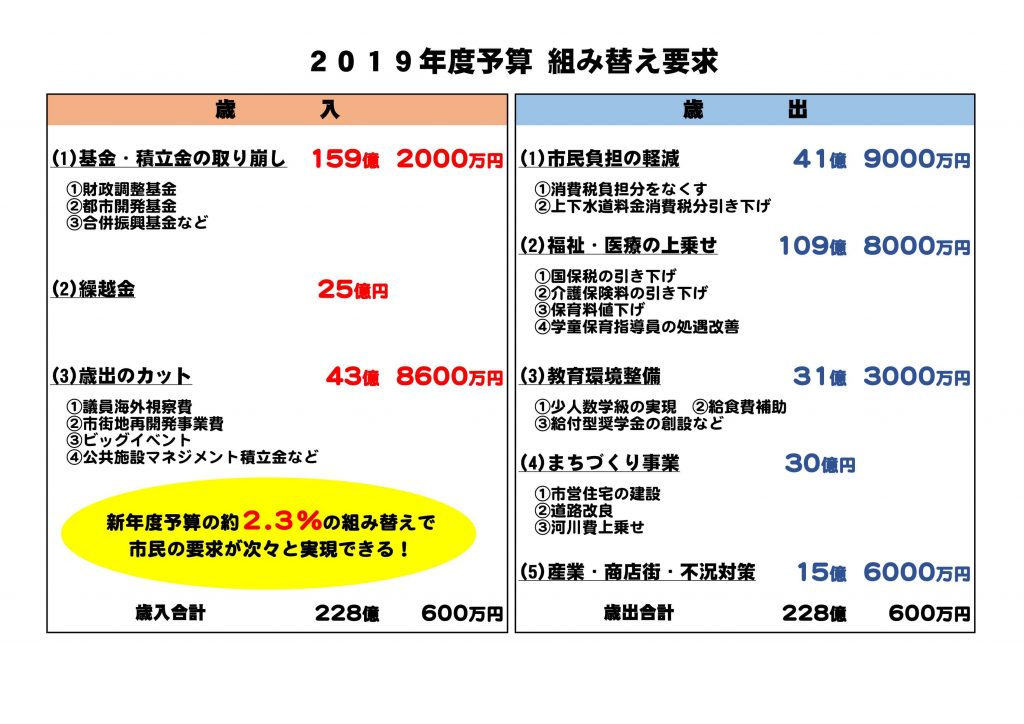6月議会*一般質問 不登校の子どもと保護者の声を聞いて
6 月10 日、6 月議会の一般質問で、とばめぐみ市議が初質問にたちました。とば市議は選挙中に公約した「子どもがみんな笑える日まで」という立場で保育・不登校・学校建設問題を質問しました。
不登校の児童・生徒数は5 年連続で増加し、全国で14 万4000 人です。本市でも、小学校で269 人、中学校では850 人の不登校児童・生徒がいます(2017 年度)。
とば市議は、埼玉県が12 年間続けている「保護者と教師のための不登校セミナー」で親たちから寄せられた声を紹介しながら、子どもを学校に適応させることを目的とし、教室に戻そうと無理解な対応が繰り返されていることを問い、教育機会確保法の付帯決議の観点から、子どもの思いをくみ取り無理な登校刺激をしないこと、学校から子どもを排除しないこと、その子が見つけた居場所を大事にすること、の3 点が不登校の子どもにとって大事だと述べました。
そして市に対し、県のように行政・民間・保護者が連携した話し合いを重ねることを求めましたが、市は「学校は適切に対応している」と言い切り、「民間フリースクールと協議会を重ねている」と答弁しましたが、この協議会には保護者の団体は入っていません。当事者の思いを聞こうともしない姿勢が浮き彫りとなりました。
公立の認可保育所を増やして
今年度、認可保育所に申し込んでも入れなかった子どもは2589 人。市は待機児童を393 人と発表しましたが、実態とかけ離れています。とば市議は、市民の切実な声を紹介しながら、あらためて認可保育所の増設、とりわけ公立保育所の建設を求めましたが、市は「公立保育所に比べて短期間で整備でき、特色ある保育を提供できる」と民間での整備を強調し、公立はつくらないとの姿勢を変えませんでした。
今年10 月からはじまる幼児教育・保育の「無償化」は、「認可外保育施設指導監督基準」すら満たさない認可外保育施設や、企業主導型保育施設も公的給付の対象とします。企業主導型保育施設は、政府が待機児童対策の切り札としたものの、全国で定員割れ、突然の閉園などが問題視されています。
とば市議は「保育所は子どもが1日を過ごす大事な場所。市の指導監督を受けない保育施設は公的給付の対象とすべきではない」と市の姿勢を質しました。
市は企業主導型保育施設についても「本市の待機児童解消のための保育の受け皿の1つ」「無償化の対象とし、指導監督を充実させていく」と答弁しました。
小学校建設を急いで
最後にとば市議は、見沼区の過大規模校の問題をとりあげました。大和田駅の危険な踏切を渡る子どもたちの様子や、図書室を普通教室に転用している大谷小学校の実態を紹介し、2023 年開校といわれていたのに、区画整理の遅れとPFI の検討で2 年も遅れたことについて「危険な教育環境を延長してまでPFI の導入は必要ない。1 年でも早く開校を」と迫りましたが、市はコスト削減、公民連携だとして、PFI の導入と2025 年開校に固執しました。
さいたま市議会インターネット議会中継
https://saitama-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1554