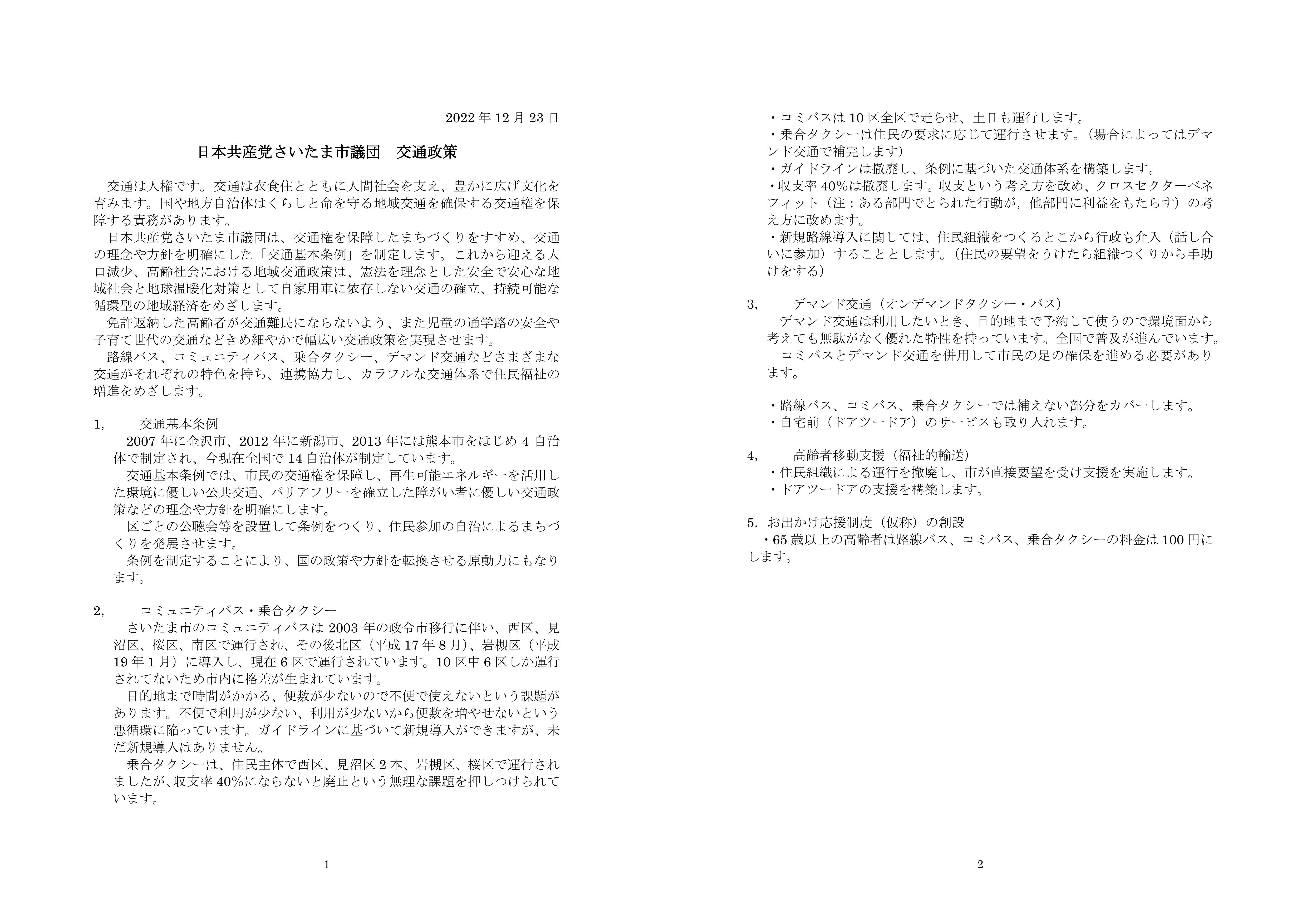12月に発表した日本共産党さいたま市議団の交通政策全文はこちらです。
2022年12月23日
日本共産党さいたま市議団 交通政策
交通は人権です。交通は衣食住とともに人間社会を支え、豊かに広げ文化を育みます。国や地方自治体はくらしと命を守る地域交通を確保する交通権を保障する責務があります。
日本共産党さいたま市議団は、交通権を保障したまちづくりをすすめ、交通の理念や方針を明確にした「交通基本条例」を制定します。これから迎える人口減少、高齢社会における地域交通政策は、憲法を理念とした安全で安心な地域社会と地球温暖化対策として自家用車に依存しない交通の確立、持続可能な循環型の地域経済をめざします。免許返納した高齢者が交通難民にならないよう、また児童の通学路の安全や子育て世代の交通などきめ細やかで幅広い交通政策を実現させます。路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー、デマンド交通などさまざまな交通がそれぞれの特色を持ち、連携協力し、カラフルな交通体系で住民福祉の増進をめざします。
1.交通基本条例
2007年に金沢市、2012年に新潟市、2013年には熊本市をはじめ4自治体で制定され、今現在全国で14自治体が制定しています。
交通基本条例では、市民の交通権を保障し、再生可能エネルギーを活用した環境に優しい公共交通、バリアフリーを確立した障がい者に優しい交通政策などの理念や方針を明確にします。
区ごとの公聴会等を設置して条例をつくり、住民参加の自治によるまちづくりを発展させます。
条例を制定することにより、国の政策や方針を転換させる原動力にもなります。
2.コミュニティバス・乗合タクシー
さいたま市のコミュニティバスは2003年の政令市移行に伴い、西区、見沼区、桜区、南区で運行され、その後北区(平成17年8月)、岩槻区(平成19年1月)に導入し、現在6区で運行されています。10区中6区しか運行されてないため市内に格差が生まれています。
目的地まで時間がかかる、便数が少ないので不便で使えないという課題があります。不便で利用が少ない、利用が少ないから便数を増やせないという悪循環に陥っています。ガイドラインに基づいて新規導入ができますが、未だ新規導入はありません。
乗合タクシーは、住民主体で西区、見沼区2本、岩槻区、桜区で運行されましたが、収支率40%にならないと廃止という無理な課題を押しつけられています。
・コミバスは10区全区で走らせ、土日も運行します。
・乗合タクシーは住民の要求に応じて運行させます。(場合によってはデマンド交通で補完します)
・ガイドラインは撤廃し、条例に基づいた交通体系を構築します。
・収支率40%は撤廃します。収支という考え方を改め、クロスセクターベネフィット(注:ある部門でとられた行動が,他部門に利益をもたらす)の考え方に改めます。
・新規路線導入に関しては、住民組織をつくるとこから行政も介入(話し合いに参加)することとします。(住民の要望をうけたら組織つくりから手助けをする)
3.デマンド交通(オンデマンドタクシー・バス)
デマンド交通は利用したいとき、目的地まで予約して使うので環境面から考えても無駄がなく優れた特性を持っています。全国で普及が進んでいます。コミバスとデマンド交通を併用して市民の足の確保を進める必要があります。
・路線バス、コミバス、乗合タクシーでは補えない部分をカバーします。
・自宅前(ドアツードア)のサービスも取り入れます。
4.高齢者移動支援(福祉的輸送)
・住民組織による運行を撤廃し、市が直接要望を受け支援を実施します。
・ドアツードアの支援を構築します。
5.お出かけ応援制度(仮称)の創設
・65歳以上の高齢者は路線バス、コミバス、乗合タクシーの料金は100円にします。