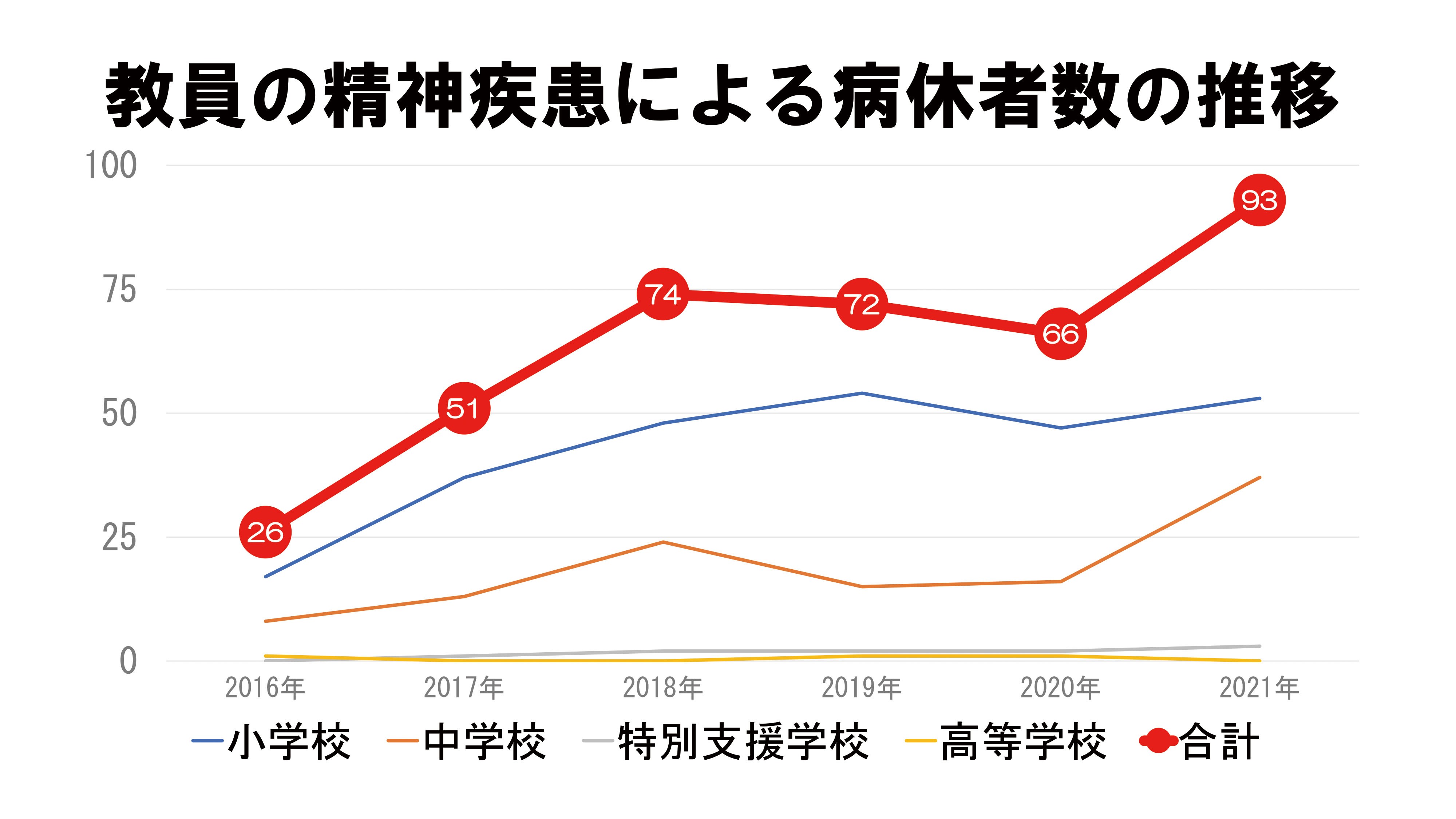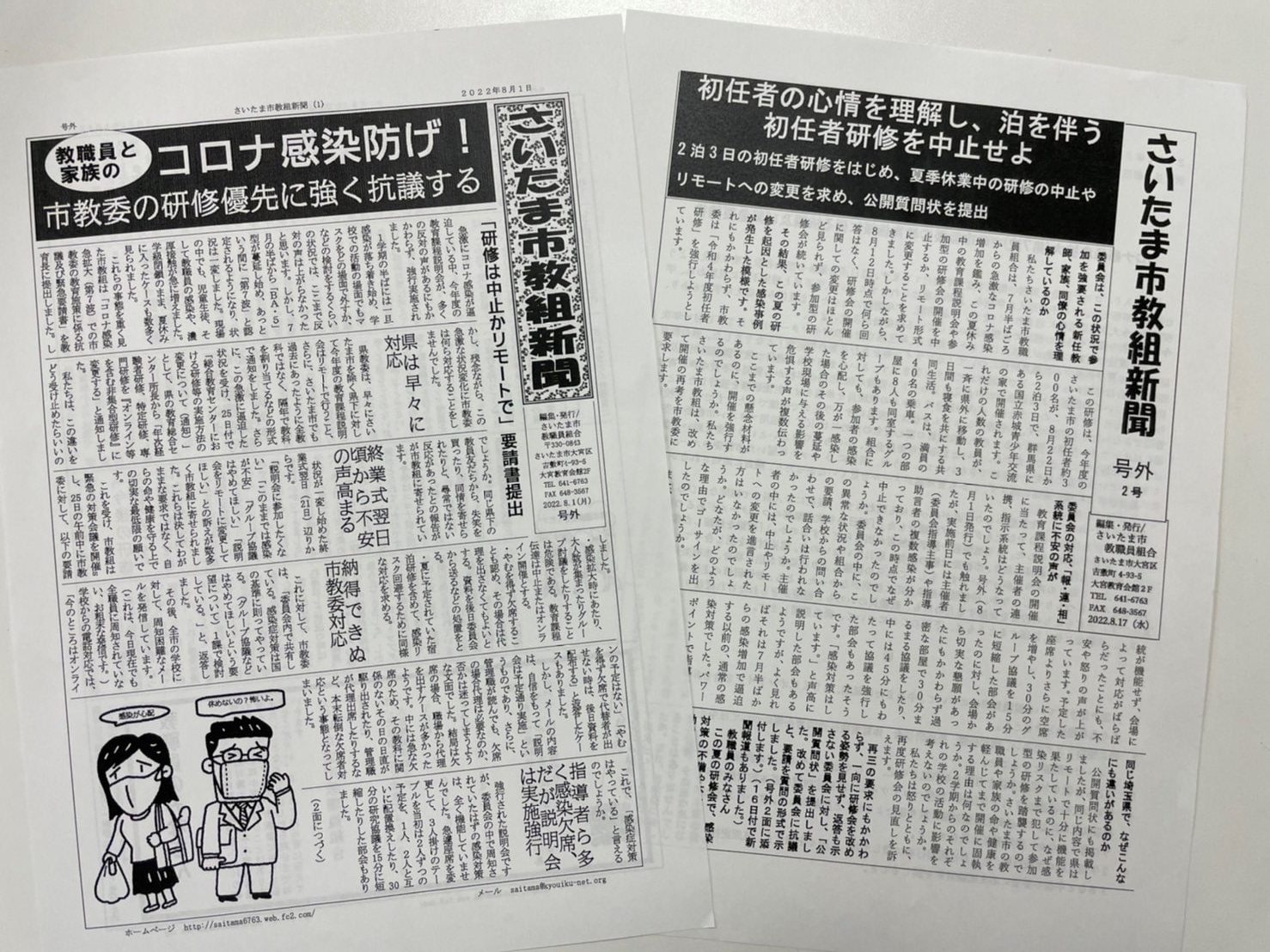阪本議長に申入書を手渡すとりうみ団長(中央)ととば市議
安倍元総理の銃撃事件をきっかけに、統一協会と政治家との関係性がクローズアップされています。市民のみなさんからは、さいたま市と統一協会に関する疑問が噴出しており、党市議団としても率先して調査・行動してきました。
8月22日、たけこし連市議は、市に対して統一協会とその関連団体からの寄付金の受け取り、企画の後援、市施設の貸し出し、市長の祝電等メッセージといった関係があるかについて調査を依頼しました。
すると、8月2日の記者会見では「統一協会との関わりはない」と述べていた清水勇人市長が、9月1日の記者会見で統一協会系団体のイベント(ピースロード)から表敬訪問を受けていたことを自ら認めました。しかも、市長が記者会見で述べた調査項目は、たけこし市議が依頼した調査項目と完全一致しています。調査依頼に応じる過程で関わりが発覚し、議会前に自ら認めることで、リスクを回避しようとしたのでしょうか。
さらに、記者会見を受け、たけこし市議が表敬訪問時の資料を市に請求したところ、出されたのは重要な部分が黒塗りの資料でしたが、実行委員長をはじめ役員に県議が2名、市議が6名、名前を連ねていることが明らかになりました(写真)。この人物たちが誰だったのかも含めて、市民に明らかにすることが求められています。
この他にもさいたま市議2名が統一協会系の雑誌を政務活動費で購入しており、しかも定価よりも3000円~1万6000円多く支出していたことが発覚しています。
議長に調査を要請
9月6日、日本共産党さいたま市議団が、阪本克己さいたま市議会議長に対し統一協会問題について申し入れを行いました。
申し入れでは、統一協会は霊感商法や集団結婚などで多くの被害者を出しているカルト集団であるとともに、前述のように、関連団体が主催するイベントの実行委員会関係者が、県議や市議の関与によって清水勇人市長を表敬訪問していた事実を指摘しています。
そのうえで、さいたま市議会が市民の不安の声に応えるためにも、各議員の実態を調査・把握し、統一協会及び関連団体の活動に手を貸すことのないよう、議長から各会派に要請するよう求めました。
この申し入れについては、9月7日の各派代表者(団長)会議において、阪本克己議長から、「日本共産党市議団から、統一協会(世界平和統一家庭連合)との関係についての申し入れがあった」と報告されましたが、議会外の事であるとして、議長としての対応はせず、実態調査は各会派に任されることとなりました。
清水勇人市長が公務として関連団体から表敬訪問を受け、その訪問は市議が要請したものであることが分かった以上、あらためて議会として調査のうえ、その情報を公開することが必要です。