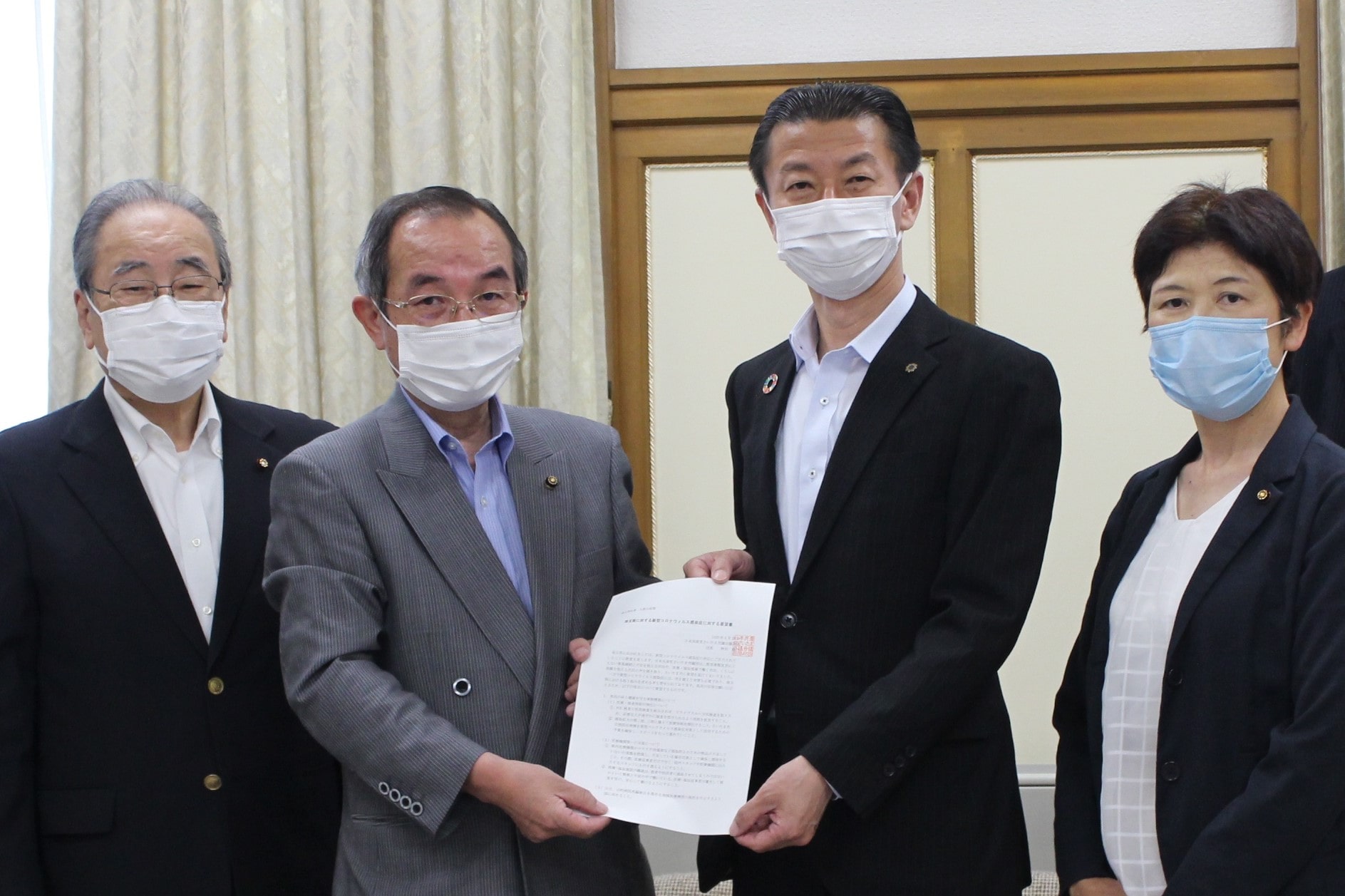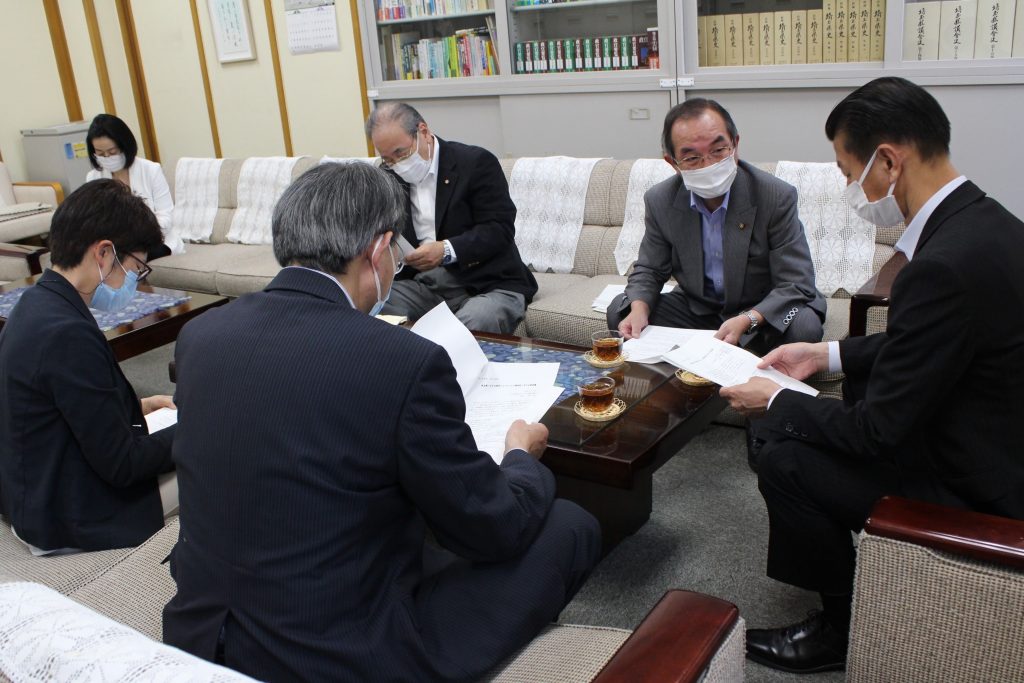さいたま市政検証vol.2 ひとごとじゃない とめよう児童虐待
7 月、東京都大田区で、8 日間もひとりきりで家に置き去りにされた3 歳の女の子が亡くなりました。大変痛ましい事件です。
今回のように母親が若く、ほかに養育者がいない場合、社会的な支援がどうしても必要です。大田区や通っていた保育所、要保護児童対策地域協議会の中で情報共有が適正にされていたのか、検証する必要があります。
児童虐待防止法は2000 年11 月に施行されましたが、その後も児童虐待は増え続け、30 年連続で増加しています。全国212 カ所の児童相談所が対応した児童虐待相談件数は15 万9850 件、さいたま市では2937 件の虐待相談件数がありました(平成30 年度)。国として、すべての子どもの命を守り切るための対策が求められますが、不十分と言わざるをえません。
党市議団はこれまで、虐待で亡くなる子どもをひとりも出さないという立場でさまざまな提案をおこない、とくに市内に2 つ目の児童相談所を増設するよう求めてきました。本市では今年4 月から、より迅速に対応するためとして児童相談所の組織を南部(旧浦和・与野)と北部(旧大宮・岩槻)のふたつの組織体制に変更しましたが、同じ建物の中であり、児童相談所を増やしたわけではありません。
妊娠期から切れ目のない支援を
昨年、さいたま市女性の活躍を推進する議員連絡会が「世田谷版ネウボラ(※)」を視察し、とばめぐみと金子あきよの両市議が参加しました。
世田谷区は「虐待防止と子育て支援はセットで行うべきである」との理念のもと、「世田谷区妊娠期から子育て家庭を支える切れ目のない支援検討委員会」を立ち上げ、地域と医療の連携で虐待を防ぐしくみ作りにとりくみました。そのなかで、専門家として日本助産師協会が大きな役割を果たしました。
専門家を中心に据えた地域との連携は、区内5カ所の各総合支所の相談窓口に、保健師などの専門職で構成されたネウボラ・チームを設置し、妊娠期から子育て期の不安や悩みに対する相談支援をおこないます。また産前・産後サービスが利用できる1 万円分の子育て利用券を配布し、区が提供する産後ケアサービスや住民主体の子育て支援活動に利用でき、地域と繋がるきっかけとなっています。
2019 年9 月議会の保健福祉委員会では、とばめぐみ市議が「世田谷版ネウボラから学び、さいたま市でも妊娠期からの切れ目のない支援のしくみを作るべき」と求めました。
児童養護施設は最後のとりで
一時保護された子どもたちは、原則2 カ月以内に家庭復帰、または児童養護施設や里親等に措置されます。さいたま市内には3カ所の児童養護施設があります。
7 月15 日、とばめぐみ市議は市内の児童養護施設を訪問し、現状と課題を調査しました。施設長からは、多くの課題を抱えた乳幼児から思春期まで、幅広い年齢の子どものケアをおこなう児童養護施設において、その処遇の低さから職員の確保が難しく、定員通りに子どもを受け入れるのが厳しい現状や、この間の新型コロナウイルス感染拡大にともなう一斉休校から、約3 カ月にわたり子どもたちが施設内で過ごすなかで、デジタル授業への対応の苦労等が切々と語られました。
児童養護施設は、保護された子どもにとって最後のとりでです。ここで働く職員にも市の「保育士宿舎借り上げ支援事業」を適用させるなど、党市議団として抜本的な処遇改善にとりくみます。
※ネウボラとは? フィンランド発祥の、妊娠期から就学前まで、ひとりの母親につきひとりの専門職(助産師や保健師)が継続的に母子とその家族の相談・支援をおこなうしくみ
■子どもの虐待相談連絡先
・児童相談所虐待対応ダイヤル/24時間・365日通話料無料/℡ 189
・さいたま市北部児童相談所/平日8:30~18:00/℡ 048-711-3917
(西・北・大宮・見沼・岩槻区)
・さいたま市南部児童相談所/平日8:30~18:00/℡ 048-711-2489
(中央・桜・浦和・南・緑区)
・24時間児童虐待通告電話/24時間・365日/℡ 048-711-6824
■さいたま市の妊娠・出産・子育ての相談窓口
・妊娠・出産の電話相談/毎週火曜13:00~16:00/℡ 840-2217
・妊娠・出産包括支援センター:助産師等の母子保健相談員等専門の職員が妊娠の届出受理や母子手帳の交付をおこなう。妊娠・出産・育児に関する相談に対応/平日8:30~17:15
西区(区役所1F)℡ 620-2705
北区(区役所3F)℡ 669-6102
大宮区(区役所4F)℡ 646-3100
見沼区(区役所1F)℡ 681-6100
中央区(区役所別館1F)℡ 840-6112
桜区(区役所3F)℡ 856-6200
浦和区(浦和区保健センター内)℡ 824-5000
南区(サウスピア7F)℡ 844-7202
緑区(区役所3F)℡ 712-1200
岩槻区(ワッツ東館4F)℡ 790-0223
・保健センター:保健師が育児不安についての相談に対応/平日8:30~17:15
西区役所保健センター ℡ 620-2700
北区役所保健センター ℡ 669-6100
大宮区役所保健センター ℡ 646-3100
見沼区役所保健センター ℡ 681-6100
中央区役所保健センター ℡ 840-6111
桜区役所保健センター ℡ 856-6200
浦和区役所保健センター ℡ 824-3971
緑区役所保健センター ℡ 712-1200
岩槻区役所保健センター ℡ 790-0222
・家庭児童相談室:児童に関する様々な相談を受付。匿名相談、電話相談も可/相談場所は各区役所支援課内/平日9:00~17:00(正午から13:00除く)
西区支援課 ℡ 620-2663
北区支援課 ℡ 669-6063
大宮区支援課 ℡ 646-3063
見沼区支援課 ℡ 681-6063
中央区支援課 ℡ 840-6063
桜区支援課 ℡ 856-6173
浦和区支援課 ℡ 829-6144
南区支援課 ℡ 844-7173
緑区支援課 ℡ 712-1173
岩槻区支援課 ℡ 790-0164
・子育て不安電話相談/平日10:00~16:00/℡ 881-0922
・なんでも子ども相談(あいぱれっと内):子どもに関するあらゆる相談。おおむね15歳までの子どもとその保護者、関係者向け/月・火・木・金曜10:30~18:30、土・日・祝9:00~16:30/℡ 762-7757/メール nandemo-kodomo@city.saitama.lg.jp
そのほかにも様々な分野の相談窓口があります。